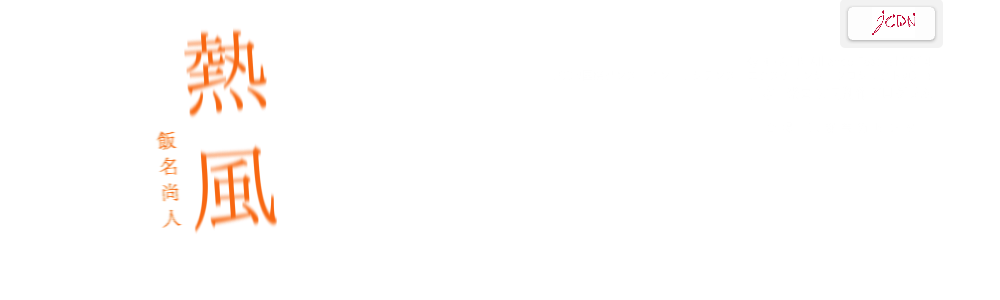新たな現実の兆すとき
文・竹田真理
この不思議な作品をどう定義づければよいだろう。音楽、写真、映像、ダンス。異なるジャンルの間を移行しながら、沖縄、モスクワ、カンボジア、キューバ、サラエボ、タスマニア、ジンバブエと視線の旅をする。会場の壁面に展示された異国の写真を見て歩き、床に座って沖縄音楽のライブを堪能する。アンコールを求める拍手が終わらぬうちに、首からカメラを提げた男が現れ、ある写真家の足跡を語り始める。観客は椅子席に移り、さらに男の話を聞く。続いて映画が上映され、見終わると会場を移動してダンスパフォーマンスに立ち会う。全体でひとつの空間を構成するようなマルチメディア・パフォーマンスとは異なり、各パートは独立した作品として成立していて、それぞれの内容とスタイルをもった見応えある作品になっている。ただし相互の脈絡は俄かには把握しがたく、いわば直観と力技で一つにまとめ上げられている。
 写真家・平野正樹が実際に使っていたライカM6
写真家・平野正樹が実際に使っていたライカM6
登場するミュージシャン、写真家、俳優、ダンサー、パフォーマーは、全体を構想した飯名尚人が、自身の人生で出会い、強く感銘を受けた人物たちだ。長い活動歴と重量級の存在感、そしてアーティスト個人の美学にとどまらない社会的な視野をもった表現者たちである。そのような彼/彼女らを一堂に呼び寄せることで、世界の在りようを鷲掴みにして示すこと。当日配布された飯名の創作ノートからは、そうした純粋な野心のようなものが読み取れる。作品としての整合性はさておいても、今表現しなくてはならないことを確信犯的に伝えようとする、その動機の強さは、本作品の大きな魅力にも力にもなっている。もしかしたら、世界や歴史に関わる視点で今起きつつある何かを考察するには、ダンスとか演劇、パフォーマンスといった単独の形式の洗練や先鋭化では限界があるのかも知れない。舞台芸術の言語を巡る隘路を脱け出し、議論を広い視野へ連れ出していく、そんな発想の自由さと構想のスケールの大きさを感じさせながら、公演は二時間半に及び、後には長い旅を終えたような充実した手応えが残った。
「世界へ向けてどのように視線を向けるか」は、本作の隠れたサブ・テーマといえる。写真家や映像作家がカメラのファインダーを通して見る世界は、作品中の大きな柱となっている。ミュージシャンのライブはカメラ・アイとは無関係のようだが、しかし沖縄というトポスに視座を構え、その一点から定点的に世界を見続ける姿勢は、やはり「視線」の構え方の一つの態度であり方法、もしくは流儀といえる。また、第三部の映像作品の中には双眼鏡をのぞく少女が出て来るが、レンズの先に様々な景色を見る姿は、全編を貫く象徴的なイメージになっている。世界に対していかなる距離、角度、深度で視線を構えるのか、定点的か流動的か、俯瞰するのかクローズアップか――そこには視線の身体性とも言うべきものが現れるが、そうした様々な視線のあり方、物の見方、見え方、視界に捉えられる景色の差異が、ジャンルの違いとともにこの“舞台作品”で体験されることになる。
 第3幕で上映された短編映画「熱風」より
第3幕で上映された短編映画「熱風」より
「視線」に関してさらに言えば、双眼鏡の先、レンズの向いた先々にクローズアップされる世界の細部、自分とは関わりのない遠い場所での出来事だったはずのものが、何かをきっかけにぐっと解像度を上げて迫ってくる、その瞬間のざわめくような世界の手触りを伝えること。タイトル『熱風』は、おそらくこのような、新たなリアリティが開かれる瞬間の衝動や予感、兆しのようなものを指している。たとえば自分が他の誰かにとって他者であることを突き付けられたとき――それは認識していた物事が全く意味の異なる事実として現れ直してくる瞬間であり、ときに困惑や苛立ちを伴うことがあるとしても、そこにある新しい現実が開かれる兆しにほかならない。本作に登場するアーティストたちは、それぞれがそのような兆し=熱風をもたらす存在として、飯名自身の直観によってこの場に召喚されている。
 撮影:平野正樹
撮影:平野正樹
さて、沖縄音楽のミュージシャン、Shinbowは、他者たる沖縄を象徴するような存在だ。三線を弾き、一晩中でも語り尽くせぬほどのエピソードを抱えた語り部Shinbowは、親密な口調でベトナム戦争時にさかのぼる自らの出自を語り、沖縄独自の言語や文化の危機を語り、本土からやってくる音楽産業への批判を語る。それぞれの話のオチには人の世のままならさ、哀しみ、ユーモア、少しのシニカル、人々のしたたかさと政治性が滲み出る。「かつて沖縄では各家で豚などの家畜を飼っていて、苦しませずに一刺しで屠る技をもった職人がいた。太平洋戦争時の集団自決の際、彼はその技で家族を一人ずつ手に掛けた。急所を外すと豚は血を吹きだして走り回る。職人は自分の自決に失敗し、掻き切った喉は以来声が出ない。声の出ない唄者として三線を弾いている。」生きた歴史の証言でもあるSinbowの語りは、沖縄の強いられた歴史を静かに糾弾していて言葉もないが、見て取るべきはShinbowのアーティストとしての構え方だ。憤りや諦め、失望と希望、或いは複雑な権力や利害の関係が深く陰影を刻む沖縄という場所。そこを自らの立ち位置としつつ、明るく抜ける三線の音とともにするりと生き延びてみせるかのようだ。人は一筋縄ではいかないし、世界はのっぺりとした一枚の地図ではない。
一方、写真家の目は世界を経めぐる運動性の中にある。70年代、政治の季節の波を受けた世代、黒いライカを手にした青年は、「この鉄の箱に世界を封じ込めてやろうと」思い、「社会主義の終わりを見ようと」モスクワへ旅立つ。体制崩壊直前のゴーリキー広場でスターリン像が続々集められる光景を目にし、以降、クメールルージュのカンボジア、カストロの革命とアメリカ文化の置き土産が混在するキューバ、ベルリンの壁崩壊後の内戦が凄惨を極めたサラエボと移動を重ねる。インターネットもソーシャルメディアもない時代、歴史を次へと大きく動かす現場――多くの場合、それは戦場である――へ身を投じていく写真家の視線は、しかし常に対象から距離をとり、歴史の瞬間を後追いするようなところがある。写真家の名は平野正樹。平野へのインタビューから飯名が起こしたテキストは、俳優、笛田宇一郎の声と語りを得て、移動する視線と思考のモノローグとして語り出される。それはつまり対象よりも主体の側の物語であり、出来事を活写するドキュメントである以上に、フィクションであるということだ。観客は写真家の内なる視座に自らの視線と思考を重ねるのである。
だからたとえばこのフィクションを、革命への潰えた夢と、その終焉を見届ける旅として聞くことも可能だ。偶然なのか、写真家の足跡は共産主義の皮肉な顛末や悲劇的な結末に見舞われた都市へと向かっていて、20世紀を大きく揺り動かした政治思想の二項対立と冷戦構造、およびその崩壊の歴史を肩越しに見ながら、モノローグは避けがたく喪失のトーンをまとう。
 撮影:平野正樹
撮影:平野正樹
フィクションは同時に、ひとりの写真家が自らの表現を求めて模索を続ける道程でもある。ライカを手にアドレナリン全開で旅立った青年は、カンボジア難民キャンプで、ます写真家としての洗礼を受ける。「悲惨なものが撮りたい」自身の欲望を知って打ちのめされるのだ。獲得したスタイルを模倣だとして捨て去り、自らの被写体と構図をキューバの「バネのある素敵な」人々の中に見出していく過程は、喜びに満ちている。他方、報道の側からも芸術の側からも「あちらの人」と見なされ、しかも時代はすでにTV報道が主流、自分は「遅れてきた写真家」だと知る。この苦い現実と自身へのアイロニーを滲ませながら、写真家はサラエボで、無数の穴=弾痕=歴史の痕跡を撮り続ける。やがてその写真集は、ある評論家の目に留まる…。平野、飯名、笛田、それぞれの経験と想像力を結集したこのモノローグは、冷戦崩壊以後の喪失と希望の物語であり、今またあらたな「以後」を生きる私たちの心を強く揺さぶるものがある。平野の足跡はやがて「国境なき写真家旅団」の結成へと向かい、モノローグは結成のマニフェストの力強い宣言で終わるが、常に出来事からタイムラグをとった主体の側=視線の物語が、ここへきて世界に参画しようとする意志をあらたにするのかとも思う。一つの歴史が終わって「以後」を、いかに意味あるものとして自らの生を関与させて生きるか。地球環境と経済の論理という新たな構造を見せ始めた世界の「現場」に参画していくための宣言は、熱く、高らかであると同時に、終わることのない写真家の習慣や生業を思わせ、自分自身にとって意味あることをただ続けていくことの愚直さと尊さを見る。ここにも熱風が吹いているだろう。
移動する視線から一転、飯名尚人による短編映画の第三部は、一つの場所にとどまり、どこにも行けない物語だ。沖縄の古びた映画館「首里劇場」は、いまだに35mmフィルムでポルノ映画を掛けているような、ここだけ時間が滞っている場所。予定された映画祭はいっこうに始まらず、本土から招かれてやってきた映画監督は停滞する時間の中に留め置かれている。監督役を演じるのは二部で写真家だった笛田宇一郎。終始憮然として煙草を吸い、場所の重力から抜け出せないまま、少しずつ沈殿していく様子だ。かたや「社会主義の終わりを見ようと思って」ベルリンへ行ったと語るトランスジェンダーなガイド役、川口隆夫は、境界を行き来する者だ。車窓からの湿った風になぶられ、常に缶ビールかドリンクの氷を口にしていて、その流動する身体と浮遊する視線に、手持ちカメラによる撮影のブレが重なる。首里劇場の誰もいないステージで、酩酊した足どりのままに踊る川口が素晴らしい。音楽はイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」、1969年で時間の止まった迷宮を歌う名曲は、時間がとぐろを巻いて澱んでいるこの場所に相応しい。これはもう一つの喪失の物語だ。100年に一度熱風が吹くという言い伝え、熱風を受けて溶ける人と溶けない人がいるという謎かけ、氷と溶けて姿を消す映画監督。時間軸を失った磁場に歴史の動く兆し=突風は訪れるのか。首里劇場は実在する映画館である。現実を鋭くみつめるShinbowとはまた違った、寓話的な時間の中の沖縄がある。
 第3幕で上映された短編映画「熱風」より
第3幕で上映された短編映画「熱風」より
ここまでの流れを強いていえば激動の戦後史、とりわけ私たちがリアルな経験として知っている東西冷戦後の現代史に、それぞれの視点から、濃淡はあれ、言及してきた本作だが、第四部にきて突如、作品は射程を広げる。それまで東西を軸に展開してきた世界の構図に、南という軸が入ってきたのだ。京都芸術センターのフリースペースの床一面にモノクロの写真が並べられ、その上でアフリカ系の女性がゆったりと踊っている。そこには20世紀という時代を抜け出し、視界が大きく切り開かれたような感覚があった。
 撮影:平野正樹
撮影:平野正樹
この新たな構図では、地球環境とグローバル経済が問題の在り処として浮上してくる。写真は「国境なき写真家旅団」結成後にタスマニアを訪れた平野が撮影した切り株の実物大のプリントだ。切り倒された樹木は安価なパルプにされ、日本でコピー用紙になる。無数に広がる切り株は、グローバル・マネーの論理がもたらす不条理の光景である。直径6mにもなるそれを真上から撮影した写真は、どこかサラエボの穴にも似て、世界をそこに映し込んでいる。飯名が「ここに必要としていた」と述べるノーラ・チッポムラの踊りは、アフリカのパーカッションを遠くに聞きながら切り株の画面を踏む。細分したパルプの紙片を散らし、豊穣への祈りと、荒廃する大地へのオマージュを踊る。ジンバブエ出身、ニューヨークで活動するチッポムラもまた境界を行き来しながら黒人の体を、アフリカを、ジェンダーを問う人である。楽園ではない南、原風景ではない南の新たな分脈が、チッポムラの踊る身体によってもたらされる。
率直に言えば、扱われるイシューの内容から、この第四部は他と切り離し、別の作品として発表されてもいいのではと思われた。だが、環境とグローバル・マネーという21世紀の問題を、歴史の大きな流れの中でヴィヴィッドに捉えるために、この大枠の設定が必要だったとすれば、それも十分に理解できることである。私たちはどのような世界の、どのような現在を生きているのか。直面する矛盾や困難に対して、第三者を決め込まず、自らをも問題を構成する当事者として、危機を共有するための視点を獲得できるか。そう問いかける切り株の風景は、今この瞬間に切り開かれる新たな現実にほかならない。ここにも熱風が吹いている。
(了)
竹田真理
東京都出身、現在神戸市在住のダンス批評家。
1999年関西に拠点を移し、コンテンポラリーダンスを中心に取材・執筆、主に東京の媒体に寄稿。国際演劇評論家協会会員。