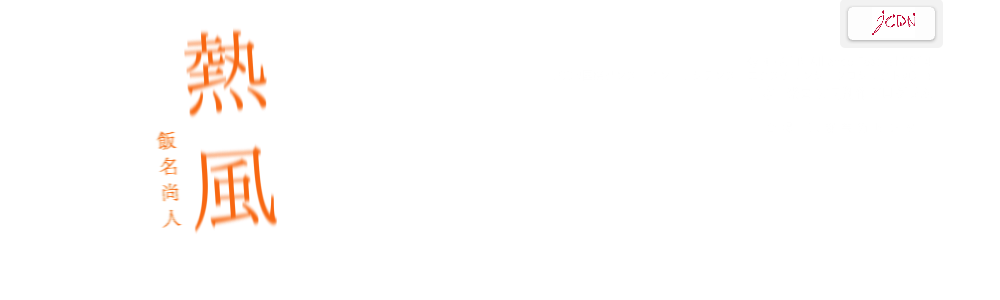「熱風」の過ぎ去った後に
文/白仁田 剛
「熱風」の公演があるという話を伺い、どのようなものなのか、初見の案内では全く見当がつかなかった。音楽と舞台、映像そしてダンスが、どのようにかかわり、何を発していくのかを想像するのが難しかった。これを知ったのは、プロジェクトの一人、写真家の平野正樹からの案内だった。八月の終わり、進捗状況の発表が京都であった。二〇一四年の京都は、短時間に物すごい雨が降ったり、また酷暑であったりと私たちを翻弄し続けたが、公演の日は比較的過ごしやすく、その日は、公演の始まる夕刻にはしのぎやすくなっていた。
 写真:平野正樹
写真:平野正樹
会場に入ると、かなりの数の写真がつり下げられており、入場の時点から公演の一つの要素を目の当たりにする。その写真は平野が今まで撮影した写真だった。公演が始まる案内があるまで、参加者は思い思いにその写真を見る。見覚えのあるイメージもある。それは写真集『DOWN THE ROAD OF LIFE』で発表されたもので、平野が振り向かれなかったと言う、一九九〇年代から撮影された東欧が中心の作品集からである。その後、二〇〇一年、この写真集の評価で平野の視野が大きく変化することになる。
公演が始まる。会場の一隅に参加者が集う。Shinbowさんの音楽と語りが静かに始まる。三線を手に、Shinbowさんの世界へ誘われる。沖縄の音階なのだろうか、でも最近聞く沖縄の音楽とは趣が違う。ともすると、歌い上げるものや激しいリズムとともに友情や愛情を歌い上げるものをよく耳にするようになった。確かに、私たちがマスメディアを通して見るそれは、沖縄のイメージとされ、それが繰り返されることで、沖縄の像がつくられていく。しかし、そこには生活が映らない。Shinbowさんの音楽は、思った以上にゆっくりで、静かだが、言葉が重い。日々の生活で感じることを、感じるままに私たちに伝える。喜怒哀楽をそのまま私たちに伝えるとShinbowさんは言うが、そう、その言葉は沖縄から直接運ばれてきた音であり言葉であり、そこを思いながら出される言葉には、勢い感情が乗って、私たちに伝えられる。
その語りの中で、私たちが思い込まされていることに気づかされる話があった。沖縄というと独特の言葉があり、そういう独自の言葉、方言を大切にしようと盛んに言われ出したが、その子供たちが方言を習っているというのである。その方言も生活で使われるのではないようで、その土地の方言を使えるのは自分たちが最後だろうと事もなげに言われるShinbowさんの語りに、軽い衝撃を覚えた。生活の場からの報告は、余りにも断層が大きい。
突如、聴衆に混じる写真家役がひとり語りを始める。笛田宇一郎の舞台が始まる。子供のころの話、スタジオマン時代の話、一九九〇年前後の東西冷戦の終焉から始まる新たな混沌と人間本位の開発を目の当たりにし、歩き回ったときのことが語られる。これは平野正樹の今までのことなのだ。何かをするということは取り返しのつかないことにもつながり、それをとどめなくてはと焦燥感に駆られるように平野は撮影したのだろう。その中で、平野の子供時代の記憶と重なる「HOLES」がある。銃撃や砲撃であいた穴を見て、それを美しいと思う彼は、東京・中野にある水道タンクの穴を見たときの恐怖感を呼び起こす。人間のなすことを自分の目で確認し記録する、それは自分が経験し積み上げてきたことへのその時点での回答として、平野は撮影する。それがこれからどうなるのか、まさに人間の行方を写真を通して発表しようとしているとき、ある一人の男の目にとまる。笛田の舞台の最後に、私たちに演説するように訴える「国境なき写真旅団」構想。そのマニフェストを書き上げ、一九八五年に休刊となった『カメラ毎日』で最後の編集長であり、公演では「日本の有名な評論家」とされている、写真編集者の西井一夫である。西井はその後、「小さな、しかし心に深く留まるようなことを大事にしていく」(「写真の会、事始め」『写真的記憶』青弓社)ことを願い、「写真の会」という会を立ち上げた一人である。平野は、二〇〇一年、第十三回写真の会賞を、今回の公演で展示した写真集で受賞する。
そのマニフェストを読む笛田の声が、会場に響く。西井が構想したのは《国境なき写真家旅団》で、全文は『20世紀写真論・終章 無頼派宣言』にある(pp.296)。写真の会といい旅団の構想といい、西井の立ち位置はぶれない。マニフェストの冒頭には、
──国境なき写真家旅団(以下「旅団」と略す)は、名前から推測しうるように、「国境なき医師団」とスペイン内戦の折の「国際義勇軍=国際旅団」とから、みずからの名を借用して名づけられた。しかし、いま現在、そのような組織は世界のどこにもない。「ない」からわれわれがはじめるのである、ガンジーが言ったとおり、すべては1からはじまる。1さえあれば、その後に0がつけば10に、0がいくつもつけば、かぎりなく大きな数にまで発展するからだ。「はじまり」はつねにささやかで、些細で小さなきっかけからスタートする。(以下略)
とある。余りにも壮大なマニフェストなのだが、同趣旨のことはこれに限らず、西井は言い続けてきたように私は記憶している。
笛田の演説を聞いていて、不思議な感じがした。すごい堂々と朗々とした笛田の声からは、西井の姿を想像するのは難しい。だが、笛田の演説にかりて響く言葉は熱を帯び、西井のうちに秘めた思いがその場に放たれたような気になった。唐突に始まるこの旅団の構想は、写真ができること、そしてその限界の双方を見定めたものであると思っている。今、写真は複製が容易になり、誰にでもどこでも発表が可能な状況となっている。しかし、何をどう伝えるか、そのために必要なものについては、意外に検討されていない。旅団は、小さくてもそれを実践するための一つの方法であり、平野はまずはそれを自律的に実践しようとしている。いやしくも、平野がこの公演を西井が見ているのではないかと言っていたが、そう考えると、笛田の演説の力をかりて、西井が壇上で趣旨を伝えていたのかもしれない。西井が鬼籍に入って十三年が経過するが、いまだに西井の言葉が精彩を放つことを考えると、今の自分のすべのなさを恥じる。せいぜい、一さえあれば発展することだけで、その成果は余りにも乏しい。
 写真:平野正樹
写真:平野正樹
演説の余韻がさめると、短編映画が始まる。画面から感じられる湿り気のまとわりつく暑さ。その空気にやられている気だるい感覚。オカマのガイドと映画監督という、よくわからない配役や人間関係。その不確かな、つかみどころのないまま話が進む。川口隆夫演じるガイドの、ねっとりした話し方と表情が、映像にさらに湿気と暑さを加える。笛田の気難しい表情が、微妙な関係を感じさせる。映画祭で上映されるはずであった「熱風」も、映写機の不調で結局何も見られずじまい。そして町を歩き回る本人も、いつの間にかその映像から消えてしまう。私たちが手にするものは、実は実感の乏しいものではないのか。その実感とは何か、確かさとは、それがすべてであると言い切っていいのか、映像は何一つ確かさのないまま終わる。
最後のシーンで、音楽に合わせて踊るガイド役の川口の動きに、目が奪われる。ずっと風もなくまとわりついていた映像から、しなやかな動きから風が生まれ、決して心地よい風ではないものの、何かが動いていく感覚は覚える。だが、何かはわからない。やはり、実体が不確かなまま、見る側に何かを残す。消化不良なのではない、この感覚は何なのだという問いかけを、あえて自分にしたくなる。
最後に、会場を移動してチッポラさんのダンスが始まる。そのダンスをする下には、平野正樹の「沈黙の森」シリーズのプリントが置かれている。さらに、その上には、木を切り倒し、それを原料につくられた、軽い紙片が床に敷き詰められている。また、その一部には木を支える大地をあらわすのか、土が敷かれている。そこをノーラ・チッポムラが踊る。時に紙は抱えられ、宙を舞う。小さな、ノーラ・チッポムラの歓喜の声がする。時に床に倒れ、動きがとまる。「沈黙の森」は、パルプの原料となる大木を切り倒し続けた、切り株を撮影したもの。私たちは、紙の原料は木であることは知っていても、どのような木が切り倒されたのかを知らない。私たちは、その現場を知らずに、何かを知ったような顔をして紙を使う。その木の大きさを知らせるために、平野はほぼ原寸大にプリントをつくり上げる。切り株を見るだけではなく、その大きさを体感する必要がある。それに反応するノーラ・チッポムラは、限られた時間、写真から得られるものを身体化させる。目の前に見えたものから得られる内発的な印象を、外発的に表現する。そして、音楽によって、踊りが変化していく。そして最後に、また笛田が登場し、その写真家の思いが伝えられる。
その写真家は、知ったような顔をして紙を使った人たちは、見えないことに想像力が余りに働かなくなり、指摘されると、これから気をつけますと殊勝なことを言って、その場をやり過ごすという。エコブームという、何となく自然を守ろうという雰囲気に流されていることにさえ警鐘を鳴らす。自然を守るという美辞は、実は経済力によって蝕まれた一部のおこぼれであり、私たちのしていることは偽善と言っているかのようにも見える。目の前のことで判断するのは当然として、そこから見えていないものを想像し、思う力のない言葉に、人間の横暴な一面を見てしまう。一瞬怒りを覚えるのだが、反対側から見れば私もその一部になっているであろうし、私はそこに明確な回答を見出すことができない。ただ同じような暮らしを続け、無為に暮らすことしかできないのか、緩慢な堕落へと私たちは転落していっていいのか、どうしても解決できない現実を突きつけられ、私たちはどうしようもない、解決のできない絶望の中を生きていることを宣告されているのである。
だが、小さな視界の中で無為に、低温火傷のように気づかぬまま破滅へ向かってはいけないと無為な抵抗をして悶々としていると、先ほど笛田が熱演した、西井のマニフェストを思い出す。全ては1から始まる、と。空疎な大義を叫ぶ前に、1から始まると言い聞かせ、何かすることで物事は動く、しなければ何も始まらないのだと、その孤絶を受け入れて批評を続けた西井の姿を重ねてしまう。
 写真:平野正樹
写真:平野正樹
公演後の出演者の話で、音楽、写真、映像そしてダンスと、異なる表現方法がどこまでお互いに影響し合うのか、それが難しいという発言があった。異なる分野の融合によって何かを発表しようという、いわゆるコラボレーションの企画が往々にしてあるが、今回の公演はそうではない。お互いの要素を断線させないような工夫は認められる。公演を体感してしばらく時間がたってからようやく、それもおぼろげに感じられることなのだが、漠然と実感のないものを信じ込まされ、手ごたえもなく何となく与えられたものでよしとしてしまうが、実は、直に場として空間や時間をともにして、遠いところからの報告をさまざまな表現を通して思考し、会場を後にしたときに、それでは実感することとは、手ごたえのあることはと問われているのかもしれない。
それぞれは独立した表現として成立している。それを融合といった言葉で簡単にまとめてはいけない。また、私が感じたことが他者と共有されているとは思っていない。私がここに記した言葉さえ、個々人が経験を通して、それぞれが咀嚼するものであり、同一であることを期待しつつも、それを一にすることはほぼあり得ない。昨今、共感をことさらに求められる場面が多い気がするが、その求めが小さな呟きを潰し、それぞれの人へ小さな抑圧を強要する。むしろ、そこにある違和、差異を確認することも、私たちの感覚を呼び起こすための不可欠な要素である。黙殺した意見に、仮に合意を得たものよりも的確に捉えていることもあり得る。何かに合わせて高揚した一体感を刹那的に酔いしれるなら、それぞれの表現の強度を保ちつつ、それを一度参加者が享受し、そのずれや違和をそのまま時間をかけておのおのが検討して見出せればよいのではないか。そういった余韻を持つ時間さえない、すべてを筋書きどおりのものを見せられるのは、退屈ではないか。参加者にとっては少々難儀かもしれないが、公演の後に残された感覚は、一人一人に時間をかけて浸潤し、次のものを受け入れるしなやかな強さを備えることになると思う。今回の公演は、まさにそれぞれが傑出した個性のある公演だったのではないだろうか。何かの標語を見る側に強いることなく、静かに私たちに問いかけられた、公演の「熱風」にさらされた後の余韻が今も続いているようである。
(了)
白仁田 剛(しろにた・つよし)
写真観察者。「写真の会」に2002年から、2006年を除き現在まで、継続的に参加する。西井一夫氏が遺した『写真編集者』『20世紀写真論・終章』を基点に、会員の鈴木一誌氏に奨励され、写真にかかわる現場へ赴き、写真について観察を続けている。