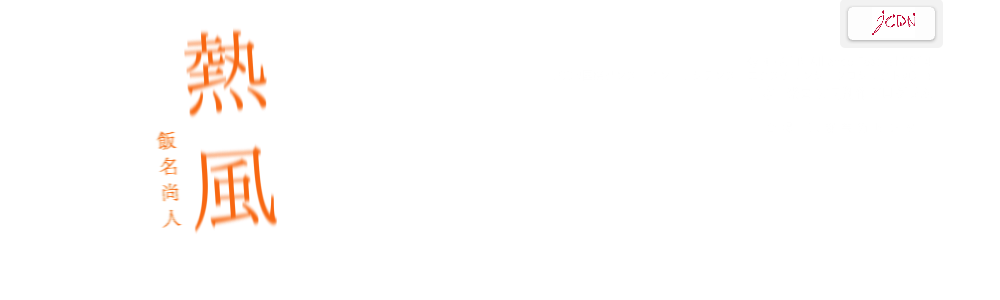100年に1度ということ
文/隅地茉歩
作品鑑賞の場におもむいた時、冒頭からしばらくの間の作業として、その作品の、自分にとってのリアルさの層を確かめようとしているのに気づく。そして、その値が暫定的にでも算出できると、一旦は安心する。自分が席を立つまでの間、どのようなスタンスで座っていれば良いのか、ある落ち着きが得られるからだ。

撮影:金成基
8月31日。写真が飾られた会場内で、その算出をする暇もなく聴かされたのは、Shinbow氏のライブ。濃い。風体も語りも、歌そのものも。Shinbow節にようやく馴染んだ頃、左手脇に現れたあまりにもよく響く身体から、朗々と別の声を浴びせられ、事態が飲み込めなくなる。私は穴が空くほどジロジロとその初老の男性を見た。出演者の登場だと理解するのに、一瞬の時間差が生じてしまったのだ。笛田宇一郎氏。床伝いに、壁伝いに、天井伝いに迫ってくる彼の声の波から、ようやくことばの一つ一つをキャッチできるようになった頃、映画が始まった。
そして。その映画の冒頭、100年に1度、この島には熱風が吹くと告げられる。100年に1度とは、いささか天文学的スパンだ。皆既日食、彗星の接近。生きているうちに遭遇できる保証も無ければ、身近な誰かから実体験が聞ける可能性も乏しい。だから、100年に1度という、そのスパンの設定自体で、既に現実味を剥がされる感覚に見舞われる。しかも、その風に吹かれると、溶けてしまうか否か、二つに一つらしいから恐ろしい話だ。そこでふと思い出す。そういえばいつもの作業をやっていないではないか。作品のリアルさの層を測量する作業。その値の算出をするチャンスを与えられていなかったことに、この時点で気づく。作品開始後一時間あたりだろうか。
映画の中には、目の前の笛田氏とは打って変わって、憮然としたまま延々とタバコを吸い続ける映画監督役の彼の姿がある。画面の中の、暑く埃っぽい空気を感じながら、展示されている写真を改めて眼にしてみる。撮影は平野正樹氏。弾痕も、車体も、真正面や真横からとらえられていて、見上げたり見下ろしたりするような雰囲気仕事が施されていない。真正面であることは、受け取る覚悟を強いてくる。
そんな、単刀直入な男たちに続く、4人目の男は川口隆夫氏。彼のお姉言葉と香しい湿気が、ここまでの男たちの濃さを緩和しているかというと、全くそんなことはない。麻のスーツでヒラヒラ踊る彼の佇まいそのものが充分濃いからだ。そんな目つきで笑みを浮かべないで欲しい。花が萎れそうだ。
濃さとは純度のことでもある。そんなことをぼんやり思い巡らす頃には、もうリアル値算出などどうでもよくなっていた。そもそも、算出意欲を奪われる方が喜びなのだから。
場所を変え、今度はノーラ•チッポムラのダンス。この日初めて出会う、作品中の生の女性。よく整えられ縁どられたダンスの時間が続く。ヤバイ男たちに直面させられた二時間に比べると、自分の中に少し余裕を感じてしまう。同性だからだろうか、自分もダンサーだからだろうか、別の理由からだろうか。このことは性急に結論すまい。そう心に決める。
いつの間にか場はカーテンコールになって、作者の飯名尚人氏が姿を見せた。作中誰も身につけていなかった真っ白いシャツ。それが実感を伴っていて鮮やかだ。

撮影:金成基
いくつかお仕事をご一緒することがあり、見慣れた姿であるはずの彼を、客席から見るのは初めて。飯名さんの身体は筋肉質ではない。どちらかというと華奢で、ユラユラと歩く。その後ろ姿を見るのが割と好きだ。地面を踏みしめ過ぎない感じが良い。太陽神経叢のあたりに蓄えているのかもしれないトロっとした泉から、細い糸が這い登り続けている。
この糸が曲者で、こんな作品を創ってしまうのだ。大作?スペクタクル?そんな言葉には彼は興味も無いだろう。熱風じゃなくて、やりたいのは100年に1度の作品じゃないんですか?と尋ねたら、笑われてしまうに違いない。「そんな作品見たら、やっぱり溶ける人と溶けない人に分かれるんですかね」なんて。
ワークインプログレスだった今回の上演は、更なる進展を見据えている。次回はリアル値算出の隙間があるのかどうか、首を洗って待っていることにしよう。
(了)
隅地茉歩
振付家•ダンサー。セレノグラフィカ代表。源氏物語の研究者から転身して20年、セレノグラフィカ結成から17年、トヨタコレオグラフィーアワード2005「次代を担う振付家賞」受賞から9年。不思議で愉快、明るくて恐ろしい作風の振付家。「身体と心に届くダンス」を生み出すべく公演•WS•アウトリーチに取り組み、渇望を抱えつつ年間2分の1を遠征で過ごす。京都精華大学ポピュラーカルチャー学部非常勤講師。
www.selenographica.net/